東北の秋は「芋煮会」

東北の秋といえば、紅葉、秋刀魚、そして「芋煮会」。
なかでも芋煮会は、宮城県と山形県で盛んに行われており、筆者をはじめ地元民にとっては日常生活の一部。
仙台市内の河川敷などで、毎年芋煮会を楽しんでいます。
また山形県では、毎年9月に「日本一の芋煮会フェスティバル」が開催されます。このように「芋煮会」は、東北民にとって毎年欠かせない秋の行事なのです。
本場の「芋煮会」を手軽に再現できるセットを紹介!
芋煮会を知らない人もいる

しかしこの「芋煮会」。東北以外の地域では、あまり馴染みのない言葉みたいです。
「仙台の居酒屋で”芋煮会受付中”って見たんだけど、芋煮会って何なの?」と関東の方から聞かれました。
芋煮会とは? なんて深く考えたことはありません。
この機会に改めて、芋煮会のルーツや歴史を探りつつ、芋煮会を知らない人が抱く疑問を解決していきたいと思います。
芋煮会を知らない人が抱く疑問とは?
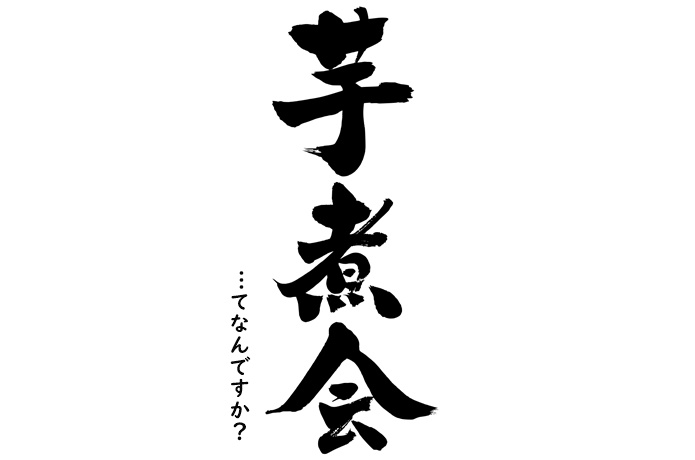
筆者や地元民にとって、芋煮会は毎年恒例のイベント。しかし芋煮会の「い」の字も出ない県からすると、「芋煮会って何?謎なんだけど。」と思うわけです。
そんな芋煮会をまったく知らない人が抱く、素朴な疑問にお答えしていきたいと思います。
芋煮会って、そもそもなに?

カンタンにいうと外で里芋を煮て食べる集まり。これが芋煮会です。


いいえ。その名の通り、芋煮会は芋が主役。芋といっても「里芋」です。バーベキューとは全くの別物ですよ。


里芋の収穫は地域によって異なりますが、10月頃が旬なのでこの時期に芋煮会が行われます。
また里芋は乾燥と寒さが苦手なので、収穫後すぐに食べるのが美味しいんですよ。


【まとめ】
芋煮会の主役は「里芋」。BBQではない。地域によって異なるが、10月中旬がオススメ。
![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)





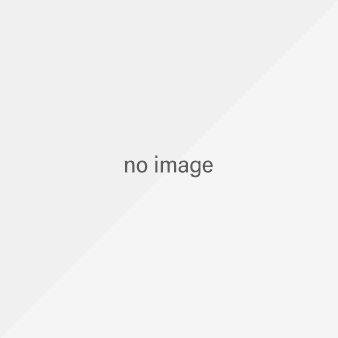
 前へ
前へ