ロマンチックな言い伝えが残る「瞑想の松」とは?

仙台市青葉区台原地区の小高い丘にそびえ立つ「瞑想の松(めいそうのまつ)」。
明治期の文芸評論家で知られる高山樗牛が旧制二高(現東北大)の学生時代、下宿先にいた女性に恋心を抱き、この松の下で瞑想にふけったといわれています。
しかしながら近年、仙台文学館の学芸室長は「瞑想していたかどうかは、はっきりしません」と話しています。
瞑想の松と命名した影には、高山樗牛の1つ後輩で、『荒城の月』の作詞で知られる詩人・土井晩翠(どい ばんすい)の存在が影響しているようです。
土井晩翠は、自身の詩集『天地有情』を高山樗牛に大いにほめられ詩人としての名声を得ました。「樗牛の早世後、旧制二高の教師として、折に触れて樗牛の功績を学生や市民に語る中で美化されたのかも」と学芸室長は推測しています。
高山樗牛とは?

高山樗牛は、1871年(明治4)山形県鶴岡市出まれの文芸評論家で文学博士。旧帝国大学の文科大学哲学科を卒業しています。
在学中の1894年(明治27)読売新聞の懸賞小説に『滝口入道』が入選し新聞に掲載。卒業後は博文館に入社し、雑誌『太陽』の編集主幹となります。ここでは、文学、哲学、美学などの評論を執筆。
初めは日本主義を主張していましたが、ニーチェの影響で個人主義へと転じます。1901年(明治34)の論文『美的生活を論ず』では、本能満足説を提唱。晩年は日蓮上人の研究を進めていました。
同年、肺結核の悪化で欧州への留学を断念。東京帝国大学の講師となったものの、翌年の1902年(明治35)31歳の若さで他界しています。
一時は伐採の危機に……?

1940年(昭和15)この台原地区に工場を建設するため、一帯の樹木を伐採する計画が持ち上がりました。そのなかには「瞑想の松」も含まれていました。
この計画を知った土井晩翠は、この工場の建設を計画した会社へ直談判するため会社社長を訪ねます。晩翠の説得に心が動いた社長は、松の保護を約束したそうです。
伐採計画は白紙になり、さらには樗牛を顕彰する碑の建立が計画されました。碑は翌年の1941年(昭和16)に建てられました。
伐採の危機を乗り越え、現在も大切に保護されている瞑想の松。さっそくその姿を見に行ってみましょう。
瞑想の松へGO!

瞑想の松のすぐとなりには展望台があり、仙台市内を一望できるビュースポット! 展望台からどんな景色が望めるのでしょうか。
まずは、瞑想の松と展望台の入口から紹介します。
瞑想の松への入口
 瞑想の松は東北医科薬科大の構内にありますが、大学の入口側からは入れません。
瞑想の松は東北医科薬科大の構内にありますが、大学の入口側からは入れません。
住宅街を通り「この先行き止まり」と書かれた電柱から階段に向かってまっすぐ進んでください。

階段を上って左に進むと案内板がありました。案内板の通り、赤い矢印の方向へ進みます。

さらに階段を上って行きます。その昔、この丘陵地一帯を天神山と呼んでいたそうです。
![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)





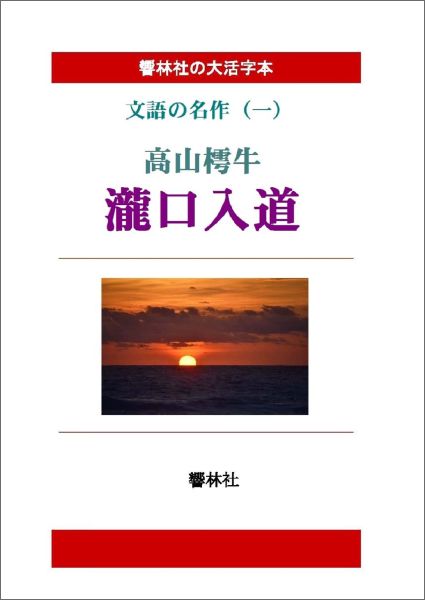
 前へ
前へ