知られざる仙台の珍スポットをご紹介

観光客がどっと押し寄せる名所よりも、来訪者が少ないクセのあるスポットが気になる……という貴方へ。
今回は観光スポットではないけれど、その土地の歴史や風土を知ることができる、仙台市の穴場スポットを「珍名所」としてご紹介します。
「珍スポット」ファンにおススメの一冊!
① ナムナム号で行く「愛子大仏」

「愛子大仏(あやしだいぶつ)」は、仙台駅から西に10kmほど離れた青葉区の佛國寺(ぶつこくじ)内ある大仏です。
天皇皇后両陛下の長女である愛子様の御生誕を祝して、2002年に建てられました。
大仏の高さは約15mあり、東大寺にある“奈良の大仏”の座高とほぼ同じ。
繊維強化プラスチック製(FRP)でつくられており、重さは約15トン。真南を向いて鎮座しています。
地元でも知らない人が多いスポットです。
ナムナム号で電車旅?

愛子大仏がある佛國寺までは、「ナムナム号」というスロープカーで向かいます。全長85メートル、速度は毎分40m。定員は9名まで。
乗り場に設置された呼び出しボタンを押すと、ナムナム号が上から降りてきます。
行先は「駐車場」「霊園」「佛國寺」の3つ。「佛國寺」のボタンを押すと、愛子大仏へ辿り着きます。
運賃は、お気持ちで結構ということです。
![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)






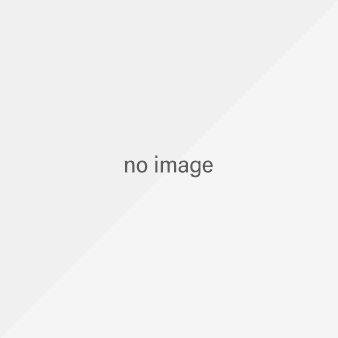
 前へ
前へ
