実在した ”福の神” 仙台四郎とは?

「実在した福の神」とも言われている、仙台四郎(せんだいしろう)。
招き猫より仙台四郎。仙台の商店に入ると、高確率で彼の写真や人形を目にするくらい地元では欠かせない存在です。
この記事では、改めて「仙台四郎」とは一体何者なのか、なぜ福の神と呼ばれ400年以上も愛され続けているのか、その魅力をひも解いていきたいと思います。
祖先は仙台藩の砲術師
仙台四郎(本名は芳賀豊孝)は、仙台藩に仕える鉄砲鍛冶屋・芳賀家の4男として生まれました。
幕末の安政元年(1855)頃の生まれだと推測されています。
芳賀家の近くには、江戸時代から1880年代まで火の見櫓があり、現在の北一番丁通りを挟んだ北向かいの青葉区役所付近を、櫓下(やぐらした)と呼んでいました。
この櫓下に芳賀家があったため、「櫓下四郎」とも呼ばれていたとか。
芳賀家の祖先は、藩祖・伊達政宗公の代より仙台藩に仕えた砲術師だったそうです。
障がいをもっていた
四郎さんは知的障がいを持っていたようです。
ほとんど会話ができなかったという説があれば、日常会話はできたという説もあり、どこまで会話能力があったかわかっていません。
趣味は散歩
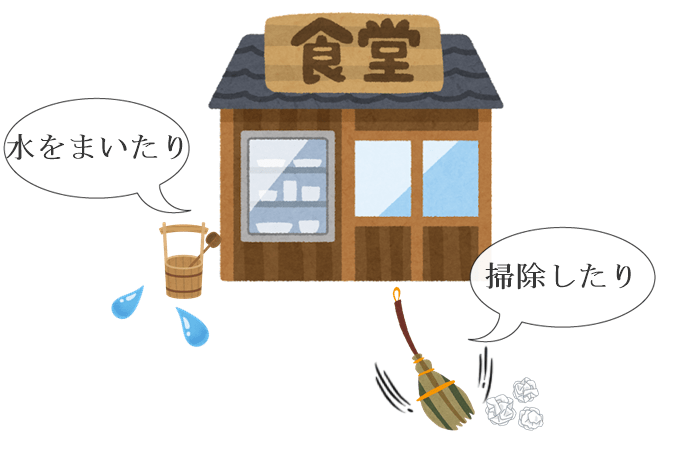
四郎さんは、笑顔でよく街中を歩き回っていたそうです。
店先にホウキが立てかけてあれば、店の前を勝手に掃除したり。店先に水と柄杓を入れた水桶があれば、勝手に水を撒いたりしていた、というような話もあります。
障がいを持っていたことから「四郎馬鹿(しろばか)」と呼ばれ、からかわれたり、いじめられたりもしたようです。
それでも四郎さんは、いつも明るく無邪気に笑っていました。そのため、どこへ行ってもほとんどの方に好かれたそうです。
子ども好きだった

四郎さんは体格がよく、丈夫であったことから「四郎さんに抱きかかえらえた赤ん坊は健康に育つ」とも言われていたようです。
わが子を四郎さんに抱いてもらおうと、どこにいっても歓迎され、町の人々に愛されていたそうです。子どもが好きで、一緒に仲良く遊ぶ姿があちらこちらで目撃されたといわれています。
立ち寄った店は繁盛する!
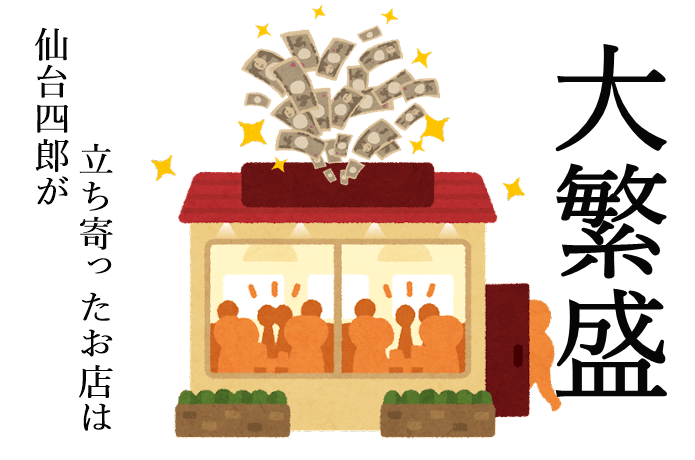
不思議なことに、四郎さんが立ち寄ったお店は大繁盛したといいます。
明治期に「四郎さんが選んで訪れる店は繁盛する」との噂が広まり、やがては地元のマスコミを巻き込んで世に知られることとなります。とくに花柳界では大人気で、モテモテだったとか。
やがて「福の神」と噂されるようになると、わざと店の前にホウキを立てかけたり水桶を置いたりする店が増え、四郎さんの気を引こうとしました。
四郎さんはとても素直な性格で、気に入らない店には呼ばれても行くことはなかったとか。そういった店は、遠からず倒産したり経営状態が悪くなったりしたそうです。
飲食代や交通機関を無料で利用できた?
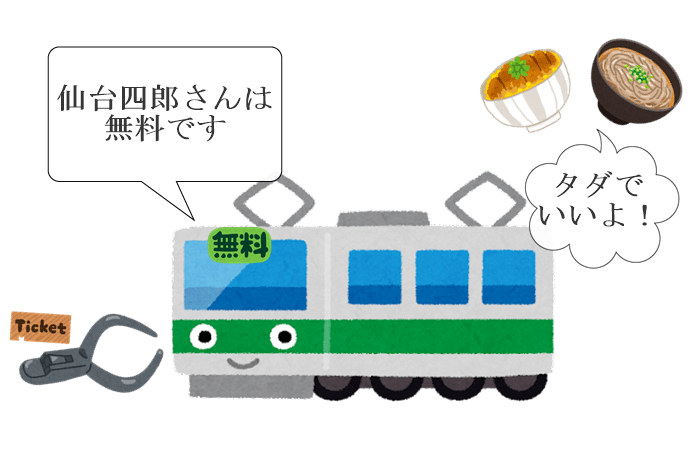
明治10年(1877)頃には、新聞に登場するほどの有名人になり、飲食代を無料とするなど四郎さんをもてなそうとするお店が出てきました。
しかし実際は、四郎さんの家人が後で店に代金を支払っていたそうです。
店側からしたら、ちゃんと代金を支払ってくれる良いお客様だったのかもしれませんね。
四郎さんは馬車や鉄道を使い、宮城県の石巻や白石、福島県の白河、さらには山形県まで足を伸ばしていたという記録もあるようです。
人々の好意から、これらの交通機関も無賃で使わせてもらっていたといわれています。人徳のなせる業、とでも言うのでしょうね。
■仙台四郎の生涯を描いた本も出ています。
明治の時代に、仙台の町で、みんなにばかにされたり、愛されたりしながら、無邪気に自由に生き抜いた四郎さん。笑いと涙に包まれた四郎さんの人生が、やさしく語りかけてくれるものは…。
![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)






 前へ
前へ