仙台の「日和山」は日本一低い山

日本全国各地にある「日和山(ひよりやま)」。宮城県には石巻市、塩竈市、仙台市、名取市に日和山があり、なかでも仙台市の日和山は標高3mの“日本一低い山”として国土地理院に認定されています。
ではなぜ日和山は全国に存在するのでしょうか? 日和山について少しひも解いてみましょう。
石巻市の「日和山」は、こちらの記事をご覧ください。
日和山は、なぜ全国にあるの?

全国の日和山は、江戸時代前期に航路が開かれた時に設置されたと考えられています。
港のそばに丘があればそこを、低地で山がない所は土を盛り上げて丘を築き、日和山としたそうです。
江戸時代は現在のようなエンジンではなく、風の力で動く帆船。主に国内での帆船輸送に携わる廻船の船乗りたちが、天候をみるために日和山を利用しました。
仙台の日和山は「いつ」からあるの?

江戸時代から明治時代の半ばまで、蒲生(がもう)地区は年貢米や塩などを塩竈(しおがま)から仙台城下町へ流通させる、舟運の重要拠点として機能していました。
しかし廃藩置県による仙台藩の消滅で、舟運は次第に衰退。その後近代化が進み、輸送手段は鉄道に代わりその役目を終えます。
この地区で舟運の仕事が無くなり、農業と漁業の両方を生業とする人や、新たに漁業へ参入する人が増えてきました。
次第に漁業が盛んとなり、明治42年(1909)頃に仙台の「日和山」が築かれました。
日和山は漁師が天候を推測し、出漁の判断をするためにつくられた※築山だったといわれています。
そもそも“日和”ってどんな意味?
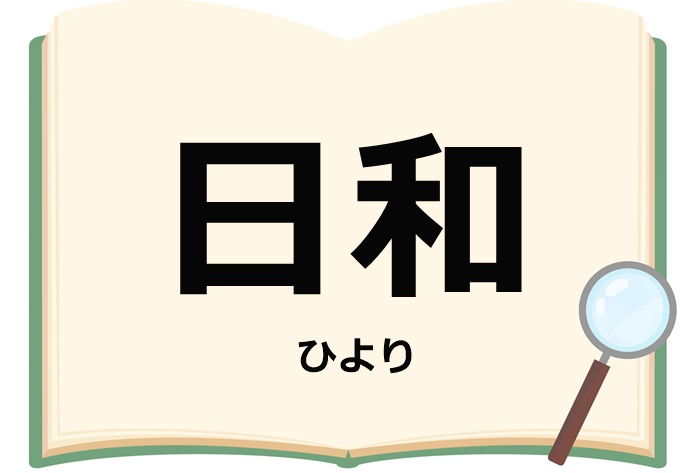
「日和」とは、行楽日和や洗濯日和など天気の良い日や、何かするのにちょうど良い天気のことに使う言葉ですよね。
日和の語源や由来を調べてみると、不思議なことに諸説ありましたのでご紹介します。
・万葉仮名説
万葉集で歌人の柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)が詠んだとされる歌の一節に、「飼飯(けひ)の海の庭好(にはよ)くあらし」というのがあります。この「庭」は海の海面を意味し、万葉仮名で「日和(にわ)」とあてられました。
ところが後に、日和を「日が和(な)いだ(おだやか)」と解釈し、日と音訓読みではない名のり(人の名に限り慣習的に使用された読み方)で使用する「和(より)」で「日和(ひより)」と読み、海の天気から天気全般を指す用語として定着したという説があります。
・日和見説
日和見説は、日和見(ひよりみ)から動詞に変化した「日和る」を語源とする説。もともと日和見は天気模様をうかがうという意味で、このことから日和見は「どっちか有利な方につこうと形勢をうかがうこと」に使われるようになったそうです。
・日寄り説
「日寄り」を語源とする説もありました。西寄り、東寄りなど方角へ片寄る意味と同じで、日(太陽)の方向へ片寄り良い天気の意味とする「日寄り」が語源とする説があります。
いずれも天気のことを指していますが、どの説が正しいのかは不明です。
それでは、日和山についてはここまでにして、さっそく「日本一低い山」仙台の日和山へ行ってみましょう。
日和山までの登山ルート

日和山へ行ったのが10月初旬。仙台市街地から車を25分ほど走らせ、15時20分頃に到着です。
気温は20℃くらいで天気は曇り。
この一帯はしばらく巨大防潮堤の工事中でしたが、令和3年(2021)3月に完成。現在は新しい駐車場や道路など、周辺環境が整備され利用しやすくなりました。
バスと徒歩でのアクセスも可能ですが、30分ほど歩きます(アクセスの詳細は記事末尾に掲載)。
![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)






 前へ
前へ